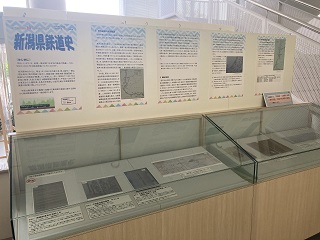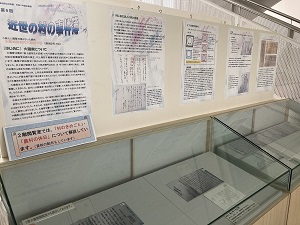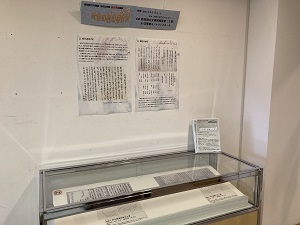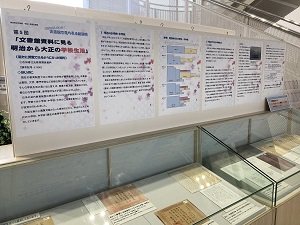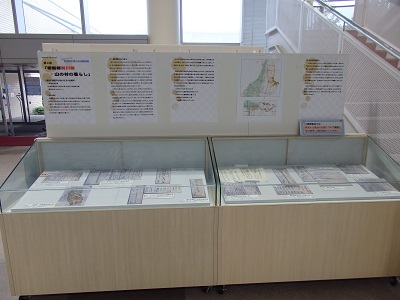文書館のイベント
第2回企画展を開催しました
令和4年度企画展「文書館開館30周年記念企画」を開催しています。
今年度の企画展では、「文書館開館30周年記念企画」と銘打って、文書館所蔵資料の中から多くの方にご覧になっていただきたいものを厳選して紹介します。全5回にわたって、その資料が語る歴史を紐解いていきます。
第2回目は「新潟県鉄道史」でした。明治5(1872)年、新橋~横浜間に日本初の鉄道が開通してから150年が経ちました。新潟県では明治19年の直江津(現上越市)~関山(現妙高市)間の開通に始まり、多くの路線が開通していきますが、それに至るまでにどのような経緯があったのでしょうか。
今は廃線となった軽便鉄道などの路線も含め、今回は県内の鉄道の歴史をご紹介しました。
展示期間は、7月12日(火曜日)~9月25日(日曜日)でした。
《図書館1階エントランスホール》
《文書館2階閲覧室》
令和4年度第1回企画展を開催しました
令和4年度企画展「文書館開館30周年記念企画」を開催しています。
今年度の企画展では、「文書館開館30周年記念企画」と銘打って、文書館所蔵資料の中から多くの方にご覧になっていただきたいものを厳選して紹介します。全5回にわたって、その資料が語る歴史を紐解いていきます。
第1回目は「新潟が熱狂!'83新潟博」でした。昭和57(1982)年の上越新幹線開通は、新潟にとって首都圏との人的・文化的・経済的交流を活発化させ、県の代表産業である農業をはじめ、工業や観光の振興を促す好機ととらえられました。昭和58(1983)年7月1日に開幕し9月4日に閉幕した県をあげてのビッグイベントである新潟博を、上越新幹線の開通から振り返ってみました。
多くの方に「懐かしい!」と思っていただける資料を展示しておりましたので、皆様ご覧になっていただけたでしょうか。
展示期間は、5月3日(火曜日)~7月10日(日曜日)でした。
1階エントランス
2階閲覧室
第6回企画展を開催しました
令和3年度企画展「お待たせしました!文書館で見られる新資料」を開催しました。
令和3年度の企画展では、「お待たせしました!文書館で見られる新資料」と銘打って、この数年で閲覧可能になった資料を全6回にわたって紹介し、その資料が語る歴史を紐解いてきました。
最終回となる第6回目は「近世の村の事件簿」でした。大瀧家は、代々、梶村(現上越市吉川区梶)の大肝煎を世襲して、地域の発展に貢献してきました。近代には実業家・政治家として活躍した大瀧伝十郎が生まれています。そのため、大瀧家には近世(江戸時代)から近代まで、1万4千点以上の古文書が残されています。
今回はその膨大な資料の中から、村に起きた事件に関わる文書をご紹介しました。
展示期間は、3月15日(火曜日)~5月1日(日曜日)でした。
図書館1階エントランスホール
文書館2階閲覧室
第5回企画展を開催しました
令和3年度企画展「お待たせしました!文書館で見られる新資料」を開催しています。
今年度の企画展では、「お待たせしました!文書館で見られる新資料」と銘打って、この数年で閲覧可能になった資料を全6回にわたって紹介し、その資料が語る歴史を紐解いていきます。
第5回目は「文書館資料に見る明治から大正の学校生活」でした。現在の教育制度では小学校・中学校が義務教育とされ、卒業後は高校、大学、専門学校など多様な学びの場が設けられています。皆さんも学校生活の思い出として、授業や部活動、運動会や文化祭などの学校行事、修学旅行などが思い浮かぶのではないでしょうか。
日本の近代教育制度は明治5年(1872年)の学制発布により始まります。学制では小学校・中学校・大学の三段階を基本とし、たびたび改定も行われました。今回は文書館収蔵資料から、明治から大正時代の小学校、中学校(現在の高等学校にあたる)の学校生活を紹介しました。
展示期間は、1月25日(火曜日)~3月13日(日曜日)でした。
図書館1階エントランスホール
文書館2階閲覧室
第4回企画展を開催しました
令和3年度企画展「お待たせしました!文書館で見られる新資料」を開催しています。
今年度の企画展では、「お待たせしました!文書館で見られる新資料」と銘打って、この数年で閲覧可能になった資料を全6回にわたって紹介し、その資料が語る歴史を紐解いていきます。
第4回目は「岩船郡関川郷~山の村の暮らし~」でした。新潟県の北端、岩船郡の東南端に位置する関川村は関川郷と呼びならわされてきた地域です。この関川村のうち江戸時代から明治22年まで小見村・内須川村であった所で、それぞれ庄屋を務めた平田家・加藤家の文書から当時の山の暮らしを紐解きました。
当時の山の暮らしを感じていただけたでしょうか。
展示期間は、令和3年11月30日(火曜日)~令和4年1月23日(日曜日)でした。
図書館1階エントランスホール
文書館2階閲覧室